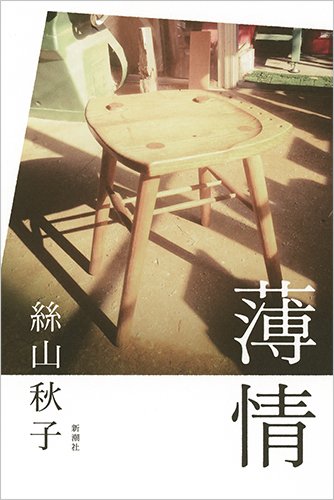北関東民のさえないソウル(絲山秋子「薄情」)
群馬、栃木、茨城、いわゆる北関東とよばれる3県は、テレビ番組のうえでは魅力のない県とされています。都道府県の魅力ランキングでは常に下位をさまよっているし、そんなありさまに自虐的ですらある。そんな場所でくらす男女は快活さからは程遠い。わたしは、群馬在住の絲山秋子さんの小説「薄情」を、そんな北関東目線でから読んだのでした。
主人公である宇田川さんは、夏は嬬恋のキャベツ農家で働き、冬は実家にもどる生活を繰り返しています。実家は神主らしいのですが、彼自身は土地の生活からは自分は浮いているようだし違和感を抱えながら生活しています。そんな彼は、鹿谷さんという人の工房に通うようになります。そこは主人公と似たような人々が集う場所になっていて、自分の行動がいちいちつつぬけになるようなきゅうくつな田舎で、その工房だけが、自分がなにものかを問われない、居心地のよさを感じるのだと。
そして、この話には蜂須賀さんという同級生が登場します。この地をいちどは離れた彼女は、遠方の生活が破綻して戻ってくる。2人が恋愛感情を募らせるわけではないけれど、土地に違和感を持ちながら暮らすところは似たもの同士です。が、やがて工房は焼けてなくなってしまう。工房に集まっていた主人公は、それまで、工房に委ねて任せっきりにしてた自分のなかの一部分を、これから自分自身でこしらえなければと知る。そんなふうにこの小説を読みました。
工房が焼けた原因は、付き合っていた蜂須賀さんと鹿谷さんのいさかいから。この土地から再び出て行こうとする蜂須賀さんに、でていくのは逃げるようなものだというような意のことを言います。 土地に縛り付けるということではなく、土地に向き合うこと=自分と向き合うことと言っているのだと思います。
私が生まれたのは栃木県の南部で、実家はいまもその地にあります。典型的な農村集落のなかに、越してきたサラリーマン家庭です。何十年とその地にすんでいても、どこか「よそもの」感は消えません。実家に帰れば、同級生のだれだれがうんぬん。という話ばかりですが、なかには同級生の刹那的なくらしなんてのも聞くのです。素性がばればれの田舎はきゅうくつで、刹那的になるのも理解できなくもない。私自身そのきゅうくつさがいやで故郷をあとにしたくらいですから。
群馬が舞台となったこの小説に、栃木出身のわたしはどこか親近感を持っていて、小説に登場する人たちのさえない感じが「すばらしい大自然に囲まれた、人情味あふれる仲間たち」なんて、すくすくとした自己肯定感など生まれようがない北関東という土地柄を表しているように、勝手に想像しています。「自分自身であること」という命題に、なやみつつも前向きに生きていく、さえなくて快活でない人たちの物語。そう読めたのでした。